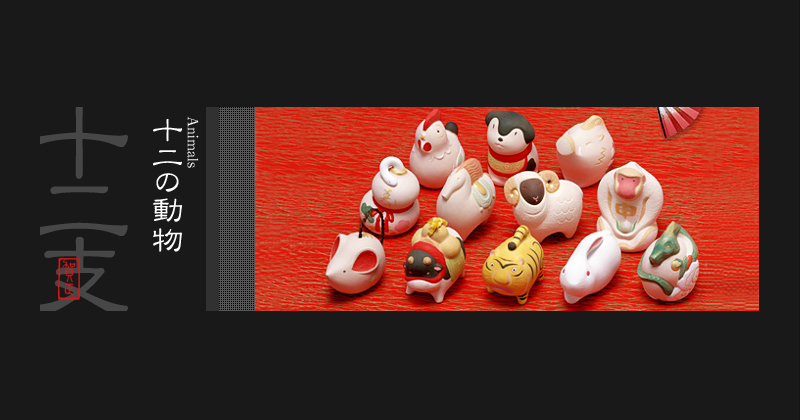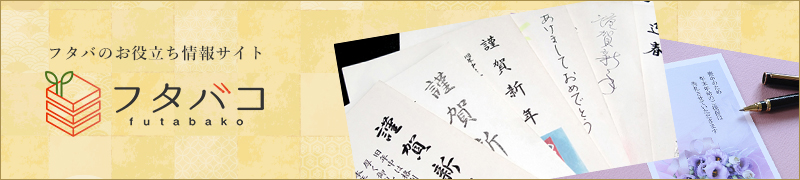干支とは
干支について
干支とはなんだったのでしょう?

「干支(えと・かんし)」とは、本来「十干十二支(じっかんじゅうにし)」の略で、十干は甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10の要素、十二支は子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の12の要素を意味し、あわせて干支と呼びます。 中国やアジアなどの地域において、主に日、月、年や時間、また角度、物事の順序などを示すのに考え出され、用いられたものです。
もとはといえば、三千年前に滅びたといわれる中国最古の王朝、殷(いん)帝国(紀元前17世紀末もしくは16世紀初頃~紀元前11世紀後半まで)にその起源がうかがえます。以降、ベトナムや北朝鮮、韓国、そして日本などに伝わりました。
日本へ伝来した時期は定かではありませんが、奈良時代より以前と考えられています。正倉院の宝物にも、十二支に関連したものが見られます。
十二支の漢字の謎。
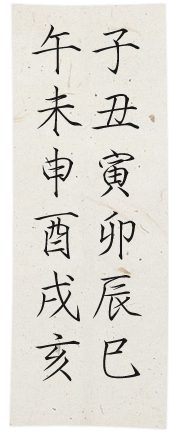
十二支に使われている文字、子・丑・寅・卯などは何故、選ばれたのでしょう?
そのほとんどは、動物とはまったく関係の無い字です。
ある説によれば、もともと十二支は月をあらわすために用いられたとされており、殷(いん)の時代にはすでにあったとされています。
これらの文字(象形文字)は、それぞれ季節に深いかかわりを持つ風物が選ばれている、あるいは人間の成長を表しているとの説も。
たとえば、「子」は幼児、「丑」は指先に力を入れて握り締めている様子・・・などなど。
いずれもはっきりしたことはわかっていません。ただ、人間の生活や日々の移ろいに深いかかわりのあるものの中から、これらの漢字が選ばれた、と想像されます。
また私たちにとっては、干支、すなわち十二支であり、つまり十二支に当てはめられた動物の総称のように考えがちですが、決してそうではありません。
動物を当てはめた謎。
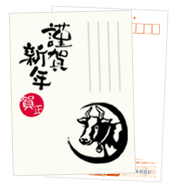
この十二支に十二の動物が当てはめられている、これは「十二生肖」などと呼びます。では何故、十二支に動物が当てはめられたのでしょうか?
これについても諸説があります。
たとえば、
農作業に欠かせない暦を覚えやすくするために、親しみやすい家畜などを当てはめた・・・
また時の為政者が一般人民にわかりやすく通達などを示すため・・・
あるいはバビロニアの十二宮の影響を受けたもの・・・
と、実にさまざまです。
しかしいずれにしても、十二支に当てはめられた動物たちは、「来年は何年だったっけ?」「私は丑年」といったやり取りや、年賀状の絵柄として、今もなお私たちの暮らしの中に深く根付いています。
選ばれた十二の動物の謎。

では、何故、子(ねずみ)・丑(うし)・寅(とら)・卯(うさぎ)・辰(たつ)・巳(へび)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(いのしし)という12種類の動物が選ばれたのでしょうか?
これもまったくわからない、というのが本当のところ。古来から中国だけでなく、わが国でもさまざまな学者がさまざまな推察を繰り広げています。しかし、それぞれの動物や文字には、人々のどのような思いがこめられているのでしょうか?
あくまでも推測の域を出るものではありませんが、ここにその一端をご紹介することにいたしましょう。
同じカテゴリーの書き物を見る